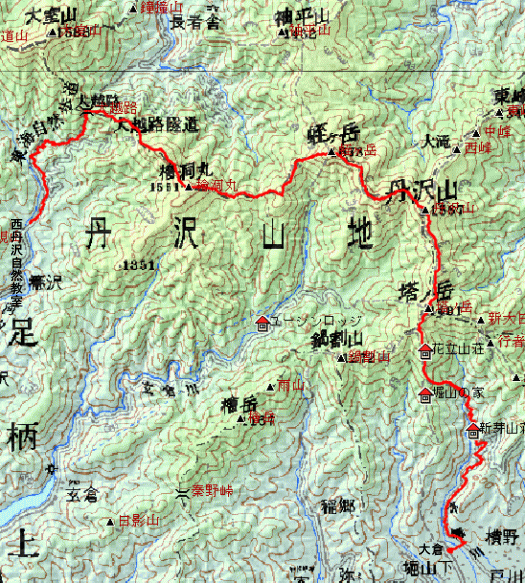| 新松田駅8時10分発の西丹沢自然教室行きバスは、この15分後にもあるためか比較的空いている。しかし途中の谷峨駅では高校生が多く乗り込み満員となる。高校生たちは丹沢湖を過ぎてから降りていった。西丹沢自然教室からバスの進行方向、北へ延びる沢沿いの林道を歩く。ツツジ新道入口の道標を右に見て進む。林道左側の白石沢沿いには三つのキャンプ場がある。バンガローが立ち並ぶキャンプ場もありこういう所で前日にキャンプを楽しんでから山登りをするのもいいな~と思う。3つ目のキャンプ場を過ぎて「私有地立入禁止」の立て札が出てくる。ここを過ぎると突当たりとなり何台かの駐車スペースがある。道標があり左へ行くと白石峠、右へ行くと犬越路である。右の犬越路方向へ進むと直ぐに大きな緑色の鉄製階段が出てくる。ここを渡り沢沿いのルートを進んでいく。 |
|
 |
| さあ、用木沢出合を出発します 撮影:どら |
|
| しばらくは沢沿いの路が続く。ダイモンジソウやイワシャジンが咲いている。沢に掛かる木の桟橋を何回か渡る。幸いなことに木の桟橋は流されてなく沢の渡渉は小さなのが1回だけであった。次第に沢の上部に達し涸れ沢になって行く。 |
|
 |
| 沢沿いや岩場の湿り気の多い所に咲くイワシャジン(岩沙参) |
|
| 犬越路直下に以前あったクマザサの藪こぎもなく割とあっけなく犬越路に到着した。穏やかで日差しがあるが靄っていて箱根方面は霞んで見える。昼の休憩をしていると続々と下から登ってきて大室山方面へ行く人が多い。 |
|
 |
| そして、小笄・大笄を目指して・・・ 撮影:どら |
|
| 犬越路からは緩やかに登って行く。山道の脇には濃紺のリンドウがあちこちに咲いている。前方には大コウゲが立ちはだかってきた。小さな登り下りを経て小コウゲの鎖場にさしかかる。更に進むと大コウゲの鎖場となる。こちらは小コウゲよりも岩場の規模が大きく何段かになっている。登って行くと大室山が大きく見え、その手前に休憩していた犬越路が見えている。小コウゲ、大コウゲを過ぎると緩やかな登りとなる。 |
|
 |
| 檜洞丸が間近い稜線の紅葉風景 |
|
| 緩やかな登りの熊笹ノ峰を越えていくと稜線には赤い実を付けた木が目立つ。葉っぱが落ちていて赤い実だけが付いている。どうやらナナカマドの実のようだ。またツツジの木と思われる真紅の紅葉も見事である。 |
|
 |
| 幾つもの険しい斜面を乗り越えてきた檜洞丸山頂直下 |
|
| 檜洞丸への最後は木製階段の登りである。登ってきた稜線が眼下に見えている。登り詰めると疎らな木に囲まれた檜洞丸山頂であった。少し休憩してから青ヶ岳山荘へと下って行く。檜洞丸山頂から蛭ヶ岳側に3分程下った所に山小屋はある。 |
|
 |
| 青ヶ岳山荘前からは明日歩く稜線が一望できる。蛭ヶ岳(左端)~塔ノ岳(右端) |
|
| 青ヶ岳山荘前からは蛭ヶ岳から塔ノ岳に至る丹沢主脈の稜線が一望できる。明日はあの稜線を歩くのだ!と思いつつ青ヶ岳山荘に入る。 |
|
 |
| そして、青ヶ岳山荘に到着^^ 撮影:どら |
|
| 山小屋は空いていて我々7名と単独行の男女2名だけであった。オーナーは高齢なためか代わりに娘さんが小屋番を務めていた。石油ストーブが付けられていて10名ほど入れる堀炬燵がある。自炊場が荷物置き場でザックはそこに置き寝床には持ってはいけない。宿の清算を済ませまだ少し早いが飲み始めることにする。掘りごたつは足が伸ばせて楽だ。炬燵の上には灯油ランプを二つ吊るしてくれた。つまみはそれぞれ持ち寄りビールを頼む人、ワインを持参の人といろいろだが、自分は持参のワインを焼酎割にする。アルコールが入るにつれ賑やかになり話がはずむ。今日の夕食はカレーライスで使い捨て発泡容器に入れられている。ワカメスープも紙コップに入れられている。水が出ない場所なのでこれも有りだろう。食後のお茶を飲みながらしばらくくつろぐ。まだ少し早いが中二階の寝床にいき横になることにする。立ち上がると頭がぶつかるのでかがんで歩く。持参のタオルを枕に巻く。敷き布団や毛布など寝具は乾燥していて清潔感がある。山小屋ではあまり眠れる方ではないが、ウトウトして眼が覚めたら午前4時過ぎであった。 |
|
| 2日目:10月19日(日)檜洞丸~蛭ヶ岳~丹沢山~塔ノ岳~戸沢~大倉 |
|
 |
| ピラミダルなシルエットの蛭ヶ岳(左)と朝日 撮影:どら |
|
| 布団の中で少しぐずぐずして朝5時に起床する。外に出ると今朝は氷点下だったと見えて木階段に霜が降りている。朝食は熱々のおでんにご飯である。おでんは発泡容器だがご飯は普通のご飯茶わんだ。これは湯のみと兼用しているためかも知れない。ご飯に持参したふりかけをかけていただく。食べている最中に真っ赤な朝日が昇ってきた。お茶を飲み早々に身支度をして外に出る。檜洞丸山頂から戻ってきた男性が「富士山が綺麗に見えています」言っている。我々は6時25分に蛭ヶ岳を目指して出発する。小屋番さんが我々を見送ってくれる。 |
|
 |
| 臼ヶ岳分岐から見る丹沢の最高峰、蛭ヶ岳(1,673m) |
|
| 最初は標高差300mほどを下る。その後は幾つかの登り下りを繰り返していく。臼ヶ岳分岐では大きな蛭ヶ岳が眼の前に聳えている。 |
|
 |
| 小鹿発見^^ 撮影:どら |
|
| ミカゲ沢ノ頭へ下って行く途中、牝の鹿2頭と小鹿1頭を見かける。そばを通り過ぎても逃げようともしない。人慣れしているのかな?ちょっと図々しい鹿だ。ミカゲ沢ノ頭は特に標識らしきものもなく気づかずに通り過ぎてしまった。ここから少し下ると蛭ヶ岳直下の鞍部に達する。蛭ヶ岳への最後は標高差300mの登りとなる。途中から鎖場が出てくる。鎖場は一つではなく二段三段とある。 |
|
 |
| 蛭ヶ岳への何か所もの鎖場を越えると、うっすら雪化粧の富士山が見えてきた |
|
| 鎖場を越えると展望が良くなりうっすら雪をいただいた富士山が見えてきた。富士山の手前には歩いてきた檜洞丸のどっしりとした山容が見えている。写真右端の山頂が檜洞丸で青ヶ岳山荘のトイレが白く見えている。その左には山小屋の屋根が青色に見えている。 |
|
 |
| 蛭ヶ岳山頂直前の登り。富士山の手前は檜洞丸 |
|
| 鎖場を越えると幾分傾斜が緩やかになり木階段の登りとなる。富士山や檜洞丸を振り返りながら一歩一歩と登って行く。そしてとうとう蛭ヶ岳山頂に到着した。檜洞丸から約3時間半の登りであった。大室山から檜洞丸そして蛭ヶ岳に至る稜線が丹沢主稜と言われている。一方蛭ヶ岳から丹沢山、塔ノ岳に至る稜線が丹沢主脈である。蛭ヶ岳からは展望の良い丹沢主脈を歩いていく。 |
|
 |
| 蛭ヶ岳から笹原の下り |
|
| 蛭ヶ岳からは開放的な風景が広がる。まさにここからは稜線漫歩といっていい程の快適な歩きだ。良く整備された笹原を下って行く。 |
|
 |
| 蛭ヶ岳からは丹沢主脈縦走路となる |
|
 |
| また写真を撮っていたら、置いてけぼりになりそうでした ガ━━(゚Д゚;)━━━ン!! 撮影:どら |
|
| 下りきると鬼ヶ岩ノ頭の登りだ。鎖が付けられているがさほどのことはない。しかし岩場の眺めと紅葉は素晴らしい。景色を眺め楽しみながら登って行く。 |
|
 |
| 鬼ヶ岩ノ頭から見た蛭ヶ岳 |
|
| 鬼ヶ岩からは下ってきた蛭ヶ岳が大きく見える。棚沢ノ頭、不動ノ峰は小さな登り下りだ。不動ノ峰を少し下った所に休憩所がある。ここで少し休憩してから先に進む。丹沢山へは標高差150mほど下って100mほど登る。丹沢山山頂は多くの登山者でいっぱいであった。我々は広場の外れの方で昼の休憩をとる。丹沢山から塔ノ岳にかけても緩やかな登り下りが続く。最後の塔ノ岳の登りだけがややきつい。塔ノ岳山頂は多くの登山者で溢れていた。特に若い人たちが多い。ここからは歩いてきた遠く遥かな檜洞丸から蛭ヶ岳、丹沢山の稜線が一望のもとだ。ここで集合撮影を撮ってから下って行く。金冷しから大倉尾根を下る。花立を過ぎ25分ほど下ると左手に戸沢への標識が出てくる。ここが天神尾根の入口である。 |
|
| 天神尾根のルートはかなり荒れていた。3年ほど前にも下ったことがあった。その時は土留めの丸太階段もきちんと付けられていた。今は丸太が外れ荒れ放題となっている。しかし丸太を目印に下って行けば迷うこともない。長い下りを下りに下ってようやく沢の音が大きくなり林道に到着した。ここからは坦坦とした林道歩きが1時間半ほど続く。途中から日が暮れてヘッドランプを使う。18時丁度に大倉バス停に到着した。とりあえず有志だけで大倉バス停前の手打そば「さか間」に入る。閉店間際で閉める支度をしていたが頼んで入れてもらう。冷たい生ビールがジーンと心に沁みわたる。新そばが旨い!蕎麦のひき方を変えて2色盛りになっている。どちらもほんのり甘く、これが新そばの味なのかなと思う。ビールとそばの味に感動しつつ、早々に引き揚げてバスに乗った。 |