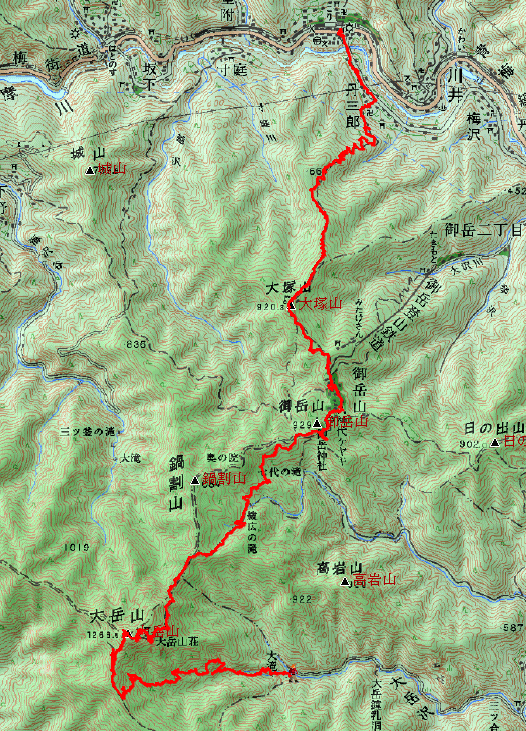|
| 林道終点から少し入ったところにある大滝 |
|
| 武蔵五日市駅前から3台のタクシーに分乗して大岳鍾乳洞の林道終点まで行く。先行した2台目のタクシーがなかなか来ない。心配して携帯電話で連絡しようとしている時に到着した。何でも以前バスの運転手をやっていてタクシーにはまだ慣れていなかったようだ。こういうことがあると3台列を作って行った方が安全だと思った。またバスの場合は大岳鍾乳洞入口で降りて林道を歩くわけだが優に40分はかかるだろう。グループの場合はこういう時にタクシーを使えるのが利点だ。林道終点からは直ぐに登山道がはじまる。沢沿いの道で木の桟橋が多い。10分ほど歩いたところで大滝が出てきた。滝の真下の木橋から全景を見ることができる。落差25mくらいだが、今日はあまり水量が多くなかったようだ。 |
|
|
 |
| 日当たりの良い斜面に咲くヤマエンゴサク(山延胡索) |
|
|
 |
| 春の便り!ダンコウバイ(檀香梅) |
|
|
 |
| 変化に富む沢沿いの道を登って行く |
|
|
 |
| 4月に入ったのに驚き!小雪渓を渡る |
|
| 大滝を見てから上に進むと、道は大滝の上を巻いて登っていきます。しばらくは沢伝いに登っていきます。4月上旬だというのに残雪が出てきました。二度にわたる今年の大雪はやはり凄かったようです。小さな雪渓を渡っていきます。 |
|
|
 |
| 沢沿いに咲くハナネコノメ(花猫の目) |
|
| 沢沿いの石にビッシリ生えているのはハナネコノメです。小さな花なので注意深く見ないと見落としてしまいます。また名前は聞いていたが実物を見て、あまりの小ささに驚く人も多いです。ネコノメソウの仲間は沢沿いや湿地など水分の多いところを好みます。特にこのハナネコノメは早春の沢の水しぶきがかかるような岩などに群生します。白い4枚のがく片と赤いおしべの葯(やく)の対比が綺麗です。小さいので写真で拡大して見ると花の形がよく判ります。ネコノメソウの仲間では最も花らしい花をつけます。 |
|
|
 |
| 馬頭刈尾根へは急登が連続する |
|
| 沢沿いを離れて広葉樹林の中を登って行きます。このあたり標高1,000m付近の山はまだ春浅く芽吹が始まっていません。急登の連続をこなし、傾斜が緩やかになる頃ようやく馬頭刈尾根に到達しました。 |
|
|
 |
| 馬頭刈尾根からの浅間尾根、笹尾根と丹沢の山並み(奥) |
|
| 馬頭刈尾根から大岳山へ向かって登って行きます。富士山の見える絶好のビューポイントがあります。ここからは三つの山並みが見えます。手前から浅間尾根、次が笹尾根、そして奥が丹沢の山並みです。そしてその上に雪をいただいた富士山が見えるはずです。しかし今日は雲に隠れて見えませんでした。大岳山の手前で分岐があります。左へ行くと御前山や鋸尾根方面、右へ行くと御岳山方面です。この道のどちらかから大岳山へ直登する道があるはずです。まず左の鋸尾根方面へ進んでみます。100mほど進んでみますが、右の尾根から外れていくようなので元の分岐に戻ります。右の御岳山方面へ進んで見ます。こんどは100m位進んだところで左に分岐が現れました。これが大岳山への直登コースのようです。急な登山道を15分ほど登ると大岳山山頂に達しました。大岳山頂は多くの人で賑わっていました。風もなく日が差して穏やかな日和です。展望は先ほどと同じで近くの山が見えるだけです。しばらくの昼の休憩後、集合写真を撮ってから大岳山をあとにしました。先ほどの直登コースと違い大岳神社へ下るコースは岩場になっています。一部鎖場もありこちらはメインのコースなので登ってくる人とのすれ違いで混みあいます。旧大岳山荘の右側にはトイレも設置されています。 |
|
|
 |
| 谷や沢沿いにはまだ雪が残る |
|
| 御岳山へ行く道は岩っぽいところが多く、右側は崖や急斜面です。岩場の所々には鎖も付けられており注意して進みます。鍋割山分岐では左の鍋割山方向へは行かず右に進みます。程なくして分岐が現れました。ここが芥場峠です。右へ行くとサルギ尾根方向、直進すると御岳山方面です。ここからは道も緩やかになり山の斜面には花が多いところです。今年はまだ少し早いようで全く咲いていません。谷にはまだ残雪があり白く見えています。右手の斜面にアズマイチゲの白いつぼみが出てきました。上の方にはカタクリの花が幾つか咲いているのが見えます。谷をまたぐ橋を渡って行きます。左側の沢に塩ビ管が出ていて水が流れ落ちています。これが地図に出ている水場のようです。 |
|
|
 |
| 咲き始めたカタクリ(片栗) |
|
| 山の斜面にカタクリがちらほらと現れてきました。スミレ類はナガバノスミレサイシンが多く、タチツボスミレやエイザンスミレは少ないです。まだ咲きはじめたばかりで、花の時期としては一週間後くらいが一番いいと思います。でもその時は雨が降るかもしれません。なので、いい時期の花に巡りあえるのも一つの運だということが言えます。 |
カタクリの不思議(蟻が種をまき、開花に8年もの年月がかかる)
カタクリは春の花としては最も人気のある花の一つです。今でも雪国では大群生地があります。昔はどこにでもある普通の草花でした。そして球根(鱗茎)から澱粉を取り片栗粉にしていました(今の片栗粉はジャガイモから作られています)。
カタクリは木々が芽吹く前の早春に花を咲かせます。木々が葉を茂らせる頃になれば、葉も溶けるようにして地上から姿を消してしまいます。その後は次の春まで地中の地下茎や球根の姿で過ごすのです。こういう草花をスプリング・エフェメラル(春の妖精)といいます。今日見た、ヤマエンゴサク、ミヤマキケマン、アズマイチゲ、カタクリなどがそうです。カタクリは発芽から7~8年もの間、1枚葉の時期があります。その後に2枚葉となりカタクリとして開花します。カタクリの種には蟻の好む匂いのする物質(エライオソーム)が付いているそうです。蟻は5月頃にカタクリの種を自分の巣に運んだ後、必要な物だけを取って種子は巣の外に散布します。蟻は不要なので捨てるのでしょうが、見方によれば種を撒いているとも取れます。この撒いた種子が発芽して7~8年の歳月を経て花を咲かせるのです。カタクリとアリ!まるでメルヘンの世界ですね。 |
|
|
 |
| 花が大きく葉が長いナガバノスミレサイシン(長葉の菫細辛) |
|
|
 |
| 名前の割には目を引く、ヨゴレネコノメ(汚猫の目) |
|
| 長尾平分岐から御岳山前を経て大楢峠分岐で鳩ノ巣へ向かいます。50mほど進むと向こうからやってきたバイクのおじさんが「通行止めですよ」といいます。聞くと途中で登山道が崩落していて鳩ノ巣へは行けないそうです。戻る途中「鳩ノ巣方面通行止め」の小さな看板がありました。他のことに気を取られてこの看板を見落としていました。やむなく、大塚山から丹三郎尾根を下ることにしました。 |
|
|
 |
| 丹三郎尾根に咲くミツバツツジ(三つ葉躑躅) |
|
| 丹三郎尾根はようやく芽吹きが始まったばかりでした。他の木々がまだ芽吹く前にミツバツツジがいち早く花を咲かせていました。まだ彩りのない山の中で明るいピンクの花が鮮やかです。そして斜面の所々に咲いていて目を楽しませてくれます。 |
|
|
 |
| 古里駅手前の多摩川も春景色 |